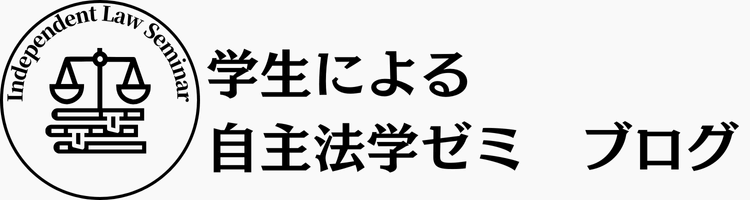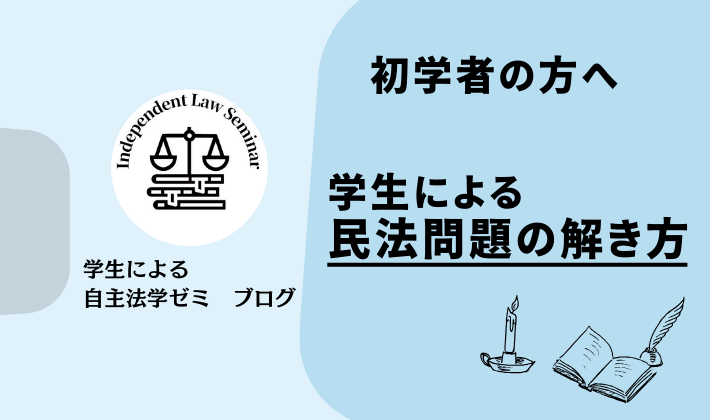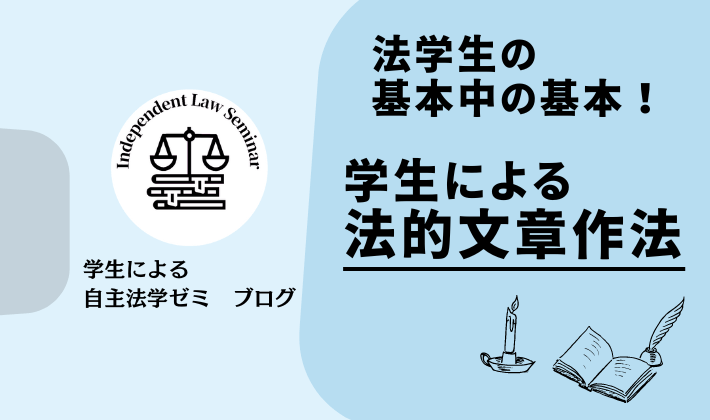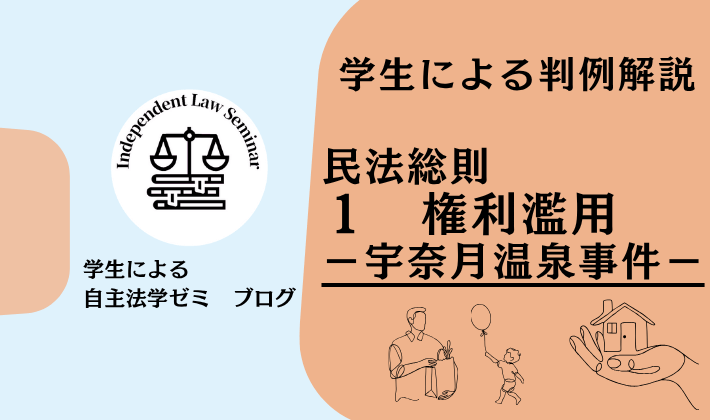はじめに
今回は、民法問題の解き方のおおわくについて、とくに答案の作成という観点から、法学生としての理解を紹介していく。
想定している読者は、民法問題について答案を作成したことがない、または、どう答案を作成すればよいのかわからないという初学者を想定している。
民法問題の解き方を紹介することで、これから学部で民法を勉強していく人や予備試験などに興味がある社会人などの人たちの理解の助けになれば幸いである。
民法問題とは
ここでいう民法問題とは、司法試験を念頭においた民法に関する試験用問題のことである。
もちろん、民法問題はその言葉の意味としては司法試験に限った話ではない。けれども、司法試験で要求される民法の問題のレベルと、一般の教養として要求される民法の問題のレベルは、全く違うものである(著者の感覚的にではあるけれども)。
そのため、一般教養感覚で民法を学んだとしても、司法試験問題は解けない。
「解けた!」と思っても、それは出題者が求めているレベルの解答にはなっていない。
きちんと司法試験を念頭に置いている民法問題の「解き方」を学ぶ必要があるのである。
民法の問題
民法問題では、法律に関する問題のうち、私法上の紛争が描かれている。
公法と私法1
法律は、公法と私法という二つの概念に分類することができる。
公法とは、国家権力と市民との間の関係を規律する法概念をいう。憲法や行政法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などがこれにあたる。
私法とは、市民と市民との間の関係を規律する法概念をいう。民法や商法などがこれにあたる。
「紛争」といっても、悲しくもニュースで見るような戦争が、起こっているわけではないし、それほど激しい物理的衝突が生じているわけでもない。
単に「争いが生じている」と認識すればそれでよい。法律の世界では、普段の生活であまり使わない日本語と接することが多いため、すこしでも疑問を抱いた語句が登場すれば、そのたびに辞書を引くことをお勧めする。
生きていると、ある語句に、気づかぬうちに辞書的な原義以上にさまざまなニュアンスやイメージが詰め込まれる。その結果、他人に通じない語句の用い方をしてしまい、あらぬ誤解を招くこともある。そうならないためにも、法律に関する文章を読む際には、普段読み慣れていない分より一層、辞書を引いて語句の意味を辞書的に理解することを徹底する必要があるだろう。
はなしをもどそう。
私法上の紛争、すなわち、民法問題では、市民同士の争いごとが記述されているのである。
具体的には、市民Xと市民Yとが互いにある土地について、「この土地は私の物だ!」と言い合って争っているといった状況が描かれることになる。あるいは、市民Aと市民Bが「前貸したお金を返してくれ!」「そんなもの借りた覚えはない!」と争っていることもあるだろう。
いずれにせよ、民法上の問題は、ある市民がもう一方の市民に対して何かを請求していることが、基本的な構造となる。
例外 ※ 混乱する可能性があるため、初学者は読み飛ばしていただきたい。
民法問題であっても、市民が国家権力に対して何かを請求していることがある(国家権力が市民に対して何かを請求している場合もある。)。
これは、国家権力が、あくまでも市民の立場として登場している場面であり、国家権力が優越的一方的立場として登場しているわけではない(いわば、私としての国家である。)。
例としては、次のような場合があげられる。
- 国家権力が、市民と、対等な立場で契約を締結し、その義務を負う場合
- 国家権力が、市民に対して、不法行為法上の責任を負う場合
他の問題との違い
憲法問題であれば、ある市民が国家権力に対して何らかの主張や請求をしていることが、基本的な構造である。
刑法問題であれば、ある市民が刑法典に違反するような行為をしていることが、基本的な構造である。
答案とは
答案とは、問に答える文章のことである。
そのため、問に答えていなければ、それは答案ではない。ただの作文である。
問われていることは、【設問】という名で独立して書かれていることもあれば、問題文の文頭ないし文末、ときには文中に書かれることもある。
いずれにせよ、「Xの請求は認められるか。」といった疑問文、もしくは「民法上の問題点について述べよ。」といった命令文の形式で、問題文のどこかに必ず書かれている。
それを見つけることが第一である。そして、その問に答えていくのである。
例えば、【設問】として「Xの請求は認められるか。」と書かれていれば、問題文中でXがしている何らかの請求は認められる又は認められないとの結論を導く文章こそが、問いに答える文章であり、答案である。
そのため、上の例のような【設問】であれば、仮に問題文中でYがVに何らかの請求をしていたとしても、無視してよい。むしろ、「Xの請求」と何らかの関係を持たない限り、無視しなければならない。
問題文に記載された事実のうち、問に答えるに際して関係のある事実を適切に挙げることができるかも、事案分析能力として法律家に求められているものである。
もっとも、うがった見方をすれば、出題者がわざわざ問題文中に示した事実であるのであるから、なんらかの意味があるはずだと警戒はした方がよいであろう。
そして、法的文章において、結論を導くための論証方法が、別稿にて紹介している法的三段論法である。
問題の解き方といっても、基本的には法的三段論法に尽きるというところがある。
まだ、法的三段論法を知らない方は、先にこちらを参照した方がよいだろう。
とはいえ、科目ごとの特徴に合わせて、具体的な解き方は変わってくる。簡単にいえば、答案全体の流れが変化する。
以下は、民法問題の特徴に合わせた具体的な解き方を紹介していく。
民法の答案
民法問題について、具体的にどうすれば問に答える文章が書けるのか。
まず、問われ方の種類としては、大まかに次のようなものがある。
- Xの請求は認められるか。
- Yは、Xからの請求を拒むことができるか。
- XY間で成立した契約の性質を答えなさい。
- 本件契約の民法上の問題点について検討しなさい。
以上、4つ挙げたが、問われ方はこの4つに限らない。実際、過去の司法試験においては、より複雑で長い設問が記載されている。
もっとも、それらを分析すれば上記の4つのいずれかに該当すると思われる。
以下、例を用いて説明していくけれども、いずれの例もだいたいの形を示すものにすぎない点に注意してほしい。
1. Xの請求は認められるか。
民法において、もっとも一般的な問われ方はこれである。
例えば、令和6年の司法試験の民法2では、この問われ方がダイレクトにされている。
〔設問1⑵〕
【事実】1から10までを前提として、次のア及びイの問いに答えなさい。
ア 請求2が認められるかどうかを論じなさい。
イ (以下、省略)。
このように、この問われ方では、ある請求が認められるかどうかをシンプルに検討すればよい。
上記の例を用いると、具体的には、次のような流れで記載することになる(なお、以降の記載も含め、あくまで例示であることに注意してほしい。)。
1 請求2が認められるためには、民法〇〇条の要件が満たされる必要がある。以下、同条の要件を満たすか検討する。
2 ⑴ 民法〇〇条の「△△△△」は、~~~~ということをいう。
⑵ 本問においては、◇◇◇◇であるから~~~~ということにあたる。
⑶ したがって、請求2は「△△△△」を満たす。
3 よって、民法〇〇条の要件が満たされているから、その効果としてXは請求2をすることができる。以上より、請求2は認められる。
記号の意味
〇〇には条文番号、
△△△△には「第三者」(民法177条)といった条文上の要件、
~~~~には、条文上の要件の解釈、
◇◇◇◇には、問題文上の具体的な事実が、それぞれ任意に入ることになる。
このように書いて初めて、問に答えたことになる。これが、この問いに対応した民法の解き方である。
また、答案上に「請求2は認められる。」とだけ書いたとしても、それは問に答えたことにはならない。
「請求2が認められるかどうかを論じなさい。」という設問は、司法試験という性質上、『解答にあたっては、いかなる法律に基づいて、いかなる要件のもとで、いかに事実が要件に該当して、いかなる効果が生じるのかについて言及しなさい。』という意味合いを当然に含んでいる。
「論じなさい。」という文言の有無にかかわらず、たとえ設問が「Xの請求は認められるか。」だけであっても変わるところはない。
文頭でこれから書く答案の方向性を簡単に示して、文中では法的三段論法を用いながら論証し、文末で問に直接対応する結論を書き記す。
これが、以降にも通じる民法問題の解き方である。
なお、「~~をすることはできるか。」や「~~との主張は認められるか。」といった設問も、これと同様の形で解けばよい。
2.Yは、Xからの請求を拒むことができるか。
これも、よくみる問われ方である。
先と同じく、令和6年司法試験の民法でも、次のように出題されている。
〔設問1⑴〕
【事実】1から5までを前提として、次のア及びイの問いに答えなさい。
ア Cは、下線部㋐の反論に基づいて請求1を拒むことができるかどうかを論じなさい。
イ (以下、省略)。
前述の1.との違いは、請求を拒もうとする立場を出発点に記述するという点だけであり、それほど大きく検討内容が変わるわけではない。
上記の例を用いると、具体的には、次のような流れである。
1 請求1が認められるためには、☆☆がないことが必要である。反論は、☆☆があると主張するものであるところ、民法〇〇条の要件を満たせば☆☆があるといえる。以下、民法〇〇条の要件を検討する。
2 ⑴ 民法〇〇条の「△△△△」は、~~~~ということをいう。
⑵ 本問においては、◇◇◇◇であるから~~~~ということにあたる。
⑶ したがって、請求1は「△△△△」を満たす。
3 よって、民法〇〇条の効果によって、☆☆があるといえる。以上より、Cは、請求1を拒むことができる。
記号の意味
〇〇には条文番号、
☆☆には条文の効果、
△△△△には「第三者」(民法177条)といった条文上の要件、
~~~~には条文上の要件の解釈、
◇◇◇◇には問題文上の具体的な事実が、それぞれ任意に入ることになる。
見ていただいてわかるように、異なるところは、答案文頭の書き方と結論の締めくくり方である。
例で用いた司法試験の問題では、「反論」が問題文上で示されていたため、上記のような例となったけれども、「反論」の記載がなくても、似たような記述をすればよい。
すなわち、反論とわざわざ書かずに、「請求が認められるためには、☆☆がないことが必要である。そのため、☆☆があれば請求を拒めるところ、民法〇〇条の要件を満たせば☆☆があるといえる。以下、民法〇〇条の要件を検討する。」とすればよい。
また、文末の結論部分では、しっかり問に答えて「拒むことができる」「拒むことができない」と記述することを忘れないように注意が必要である。
ときおり、文中の論証で満足して、問に直接答える文末の結論を書かない答案をみかける。これでは、問に答えた文章にならず、答案でなくなってしまうことに気を張らなければならない。
これに類似の問われ方として、「Xの請求に対してYがした反論の当否を検討しなさい。」というものがある。
この場合の違いは、「反論の当否」を検討する点であって、結論において「この反論が適切である。」「適切でない。」とするか、「請求を拒むことができる。」「できない。」とするかという点である。
3.XY間で成立した契約の性質を答えなさい。
この問われ方が独立で立てられているところは、そこまでみかけない。
似たような問われ方で、より多く見かけるのは、
「請求1が認められるかについて、契約の性質を明らかにしつつ論じなさい。」という形式である。
これは、前述の1.の「Xの請求は認められるか。」という問われ方に属するものである。答案の文中において、契約の性質についてきちんと記述されていればそれで足り、あくまで主題は請求が認められるか否かを論証することである。
もっとも、この場合は、その問いに答えるうえで、契約の性質を明らかにすることがほぼ必要不可欠であり、したがって、問に答えるための誘導をしてくれていると受け取る必要がある。
では、3.の「XY間で成立した契約の性質を答えなさい。」という問われ方をされた場合は、どのような解き方をすればよいのか。
例によって、司法試験の設問を引用して説明しようと思う。令和3年度の民法問題3である。
〔設問2〕
【事実】6から14までを前提として,次の⑴及び⑵の問いに答えなさい。
⑴ 契約①によるEの債務の内容及び契約①の性質を,理由を示して明らかにしなさい。
⑵ (以下、省略)。
このような債務の内容や契約の性質を問う問題は、そもそも民法のうち、債権総論および契約法という領域についての理解が必要となる。
ここでは、初学者を読者と想定しているため、内容に深入りはせず、解き方についてだけ端的に示そう。
1 契約①は、◆◆を目的とするものである。そのため、その性質としては、民法上の△△か∅∅、◎◎などの典型契約、もしくは非典型契約かのいずれかであると考えられる。以下、検討する。
2 ⑴ △△は、~~という関係が必要であるところ、契約①にそれはない。そのため、∅∅か◎◎が考えられるところ、両者では~~の有無という点に違いがある。
⑵ 契約①によって、Eは◇◇◇◇という内容の債務を負っている。これは、◆◆◆◆という意味の債務と解釈することができる。そのため、~~があるといえるから◎◎の典型契約にあたるといえる。
⑶ したがって、契約①の性質は、◎◎であるといえる。
3 よって、契約①によるEの債務の内容は◆◆◆◆という意味の◇◇◇◇である。そして、その契約の性質は、◎◎である。
記号の意味
◆◆・◆◆◆◆には事実を解釈した文言、
△△・∅∅・◎◎には民法上の典型契約、
◇◇◇◇には問題文上の具体的事実が、それぞれ任意に入ることになる。
このように、この問われ方では、いままで例と違い、文頭と文末だけでなく、文中においても構造を意識して書く必要がある。
4.本件契約の民法上の問題点について検討しなさい。
この問われ方自体は、はっきり言って漠然としている。わたしが確認した限りではあるものの、司法試験の民法問題として出題された形跡は確認できなかった。
もっとも、この出題の仕方は、大学や予備校の演習問題でしばしばみかけるものではある。
司法試験問題となると、事案が相当複雑であるために、民法問題では設問自体に誘導が施されていることが多く、このような漠然とした問い方を避けているものと思われる。
一応、会社法問題においては、過去に司法試験4で出題履歴がある。
〔設問2〕 上記の事実関係について,会社法上の問題点を検討しなさい。
このような問われ方は、多様な問題点を指摘しうるため、これらをしっかりと指摘できる能力があるかを測ったり、誘導をしたのでは受験者の差が全くつかなくなるおそれがあり、それを回避したりするためにされることがある。
こういう問われ方の際には、以下の例のように、文言通り素直に「法上の問題点」を探し、検討するという姿勢を見さればよいと考えられる。
1 事実関係に照らすと、◇◇◇◇という事実から、△△という契約が成り立ちそうである。もっとも、この契約は民法〇〇条の「△△△△」という要件を満たす必要があるところ、◇◇◇◇という事実がこれにあたるかは一概には言い難い。そこで、これについて以下検討する。
2 ⑴ 民法〇〇条の「△△△△」が設けられた趣旨は、~~~~というところにある。そして、◆◆◆◆があれば、この趣旨は達せられるといえる。そのため、◆◆◆◆があれば「△△△△」にあたると解してよい。
⑵ 本問において、◇◇◇◇という事実は、◆◆◆◆があることを意味するといえる。
⑶ したがって、◇◇◇◇がある以上、「△△△△」を満たす。
3 よって、△△という契約は成り立ち、民法上の問題はない。
このような漠然とした問われ方は、その分答え方にも多様さがより認められる。そのため、いま示した例になっていないからといって、直ちに問に答えていない文章とはなるわけではない(別に、ここで示している様々な例示通り以外は問に答えた文章ではないということを述べているわけではない。)。
読者(採点者)に、「わたしは、問題文上から民法上の問題となるところを適切に指摘して、それを検討しましたよ。」ということが伝わるように文章を書けばそれで足りる。
論じ方が一切浮かばないというのであれば、この例を応用して書けばよい。
いわゆる答案の型について
ここで、ちまたでよく言われる「答案の型」について言及しておきたい。
いままでで例として示してきたものは、それぞれがいわば民法問題における答案の型と呼べるものである。
もっとも、ときに「答案の型」という言葉が、若干独り歩きしているように思う。
答案とは、あくまで問に答えた文章であって、「答案の型」と呼ばれるものに従っていなくても、問に答えた文章といえるのであれば成り立つものである。
したがって、「答案の型」を用いて文章を作成できるようになってからであれば、べつに必ずしもこれに従う必要はない。
また、実際の問題は、誘導が多く、そのたびに解き方も誘導に合わせて修正していく必要がある。
にもかかわらず、無理に「答案の型」にしたがってしまうと、読者(採点者)からすれば、逆に暗記した論証を張り付けただけのはりぼてと認識されかねないし、そのような修正ができないようでは実際その答案は外面だけのはりぼてであろう。
いままでわたしが示してきた例も、あくまで民法問題を解いてきたことがない初学者に対して、その解き方の方向性を示したものである。
初学者がはじめから独自に問に答えた文章を書こうとしても、相当優秀でなければ支離滅裂な文章になってしまい、答案でなくなってしまう。
そのため、初学者はいわば「答案の型」を意識する必要はあるだろう。
しかし、それはあくまで初学者に限った話であって、現に司法試験にのぞもうとする段階においては、「答案の型」を意識しすぎることは、逆に有害な場面もあると思う。
初学者でない人は、「答案の型」というものを、むやみに神格化することなく、取り組んでいけばよいと思われる。
このような「答案の型」という点で一つ意識すべきことがあるとすれば、「わかりやすさ(平易性)」は絶対正義であるから、わかりにくい文章にならないように心がけるという点であろう。
思考過程
さて、ある程度「解き方」がわかったところで、実際にその中身を埋めるためにはどのように民法問題と向き合えばよいであろうか。
より具体的な思考過程は、設問をもちいないと説明が困難であるため、別稿で随時おこなっていく。
ここでは、抽象化した(あたりまえともいえるような)事項のみを記載することとする。
まず、前述の例でも示しているように、答案の流れとしては大きく次の順を意識すればよい。
- 問われていることの確認
- 問に答えるために必要な主要な争点の発見
- 争点にたどり着くまでの論理の整理
- 争点についての結論
ここでいう争点とは、問に答えるための流れのなかで、簡単に結論を導けないためもっとも争いが生じるところのことをいう。
個々別々の問題文を検討し、問に答えるために当事者同士でもっとも争いが生じえる点、すなわち法律の解釈が複雑であったり、事実の評価が難しかったりするような点があれば、それが争点であり、答案上でしっかり検討していかなければならない。
司法試験レベルの複雑な問題は、争点を検討せずして、問に答えることなど不可能であるからである。
争点と論点 -論点主義はなぜだめなのか-
本稿で「争点」と呼んでいるものは、一般に「論点」と呼ばれているものと同じ意味である。
もっとも、今日において「論点」という語は、そこだけ理解・暗記すればよくそれだけで司法試験に受かるなどという虚構として認識されがちである。この発想から、答案上において論点だけを追い求めて書いていく思考をさして、論点主義とよばれることがある。いわゆるタイパ・コスパといった効率主義の発想から論点主義に従えば合格するという認識がされてきたのであろう。
しかし、この発想は危険と思われる。
司法試験は、直接に市民と関わる法曹三者としての初歩的な能力を問うものである。市民が持つ法的苦悩は千差万別である以上、そのような様々な事実に根差してその苦悩を解決することができる能力こそが重要であり、それの初歩的な能力すらない者をわざわざ法曹三者として登用する社会的意義はないだろう。
したがって、この世に一つとして同じような事実がないなかで、いかに法的な解決を導き出せるか、その解決のために必ず答えなければならないことを発見できるかが司法試験において本来的に問われていることであるはずであって、そのような事実に根差した観察なく単に論点だけが吐き出されて終わった答案に司法試験合格の称号を与える価値は乏しいと考えられるのである。
「論点」だけを理解・暗記して詠唱できるようになったとしても、それだけで合格することはないはずで、ただの虚構すなわちフィクションにすぎない。そのため、このようないわゆる論点主義は、受験生から以上の司法試験の本質を見失わせ、結果として合格を遠のかせるような危険な発想と指摘せずにはいられないのである。
『論点だけ暗記しただけで合格した』という言説があるかもしれないけれども、それは、その合格した者が、論点の学習をしていくなかで様々な事実に根差した検討をしていける能力を知らず知らずのうちに獲得していて、それが発揮されたにすぎないのであって、『論点だけ暗記しただけで合格した』というのは単なる誤解であろう。同じ発想であまたの受験生が落ちていることに気づかなければならない。
争点も論点も、問に答える流れのなかで簡単に結論を導けないときに重要となるのであって、個々別々の問題とのかかわりを無視して論じられる代物ではない。
事実に注目し、問に答えるための流れを示していく中で、どうしても論じなければならないところがあるならばその理由を書き記してはじめて、争点・論点を語ることができるのである。
以上の意識をはっきりするためにも、本稿をはじめ当ブログでは「論点」という語は用いず、「争点」という語を用いていく。
問われていることを発見するときの具体的思考
つぎに、問われていることを正確にみつける必要がある。
問われていることを見つけるためには、設問と設問に関連する問題文上の事実に着目すればよい。
正確性については、民法に関する知識を確実に修得するにかぎる。
そして、民法問題においては、具体的に次のような思考をたどればよい。
設問に関連する条文は民法〇〇条だな。
民法〇〇条の要件は、~~~~だったな。
では、問題文を読んで要件に関係する事実を探そう。
この事実は、要件充足に役に立つ事実だな(メモをする)。
この事実は、要件充足を否定する事実だな(メモをする)。
結論は、◇◇だな。
このような思考を、必要な要件事に繰り返し行っていくことになる。
先にも述べた通り、具体的な思考過程は、設問をもちいないと説明が困難であるため、別稿で随時おこなっていきたい。
請求についての基本
最後に、民法の個別の問題に共通する基本事項について簡単に解説しておく。
- 「請求が認められる」の意味とは
- 民法における法的権利の基本的な種類
- 物権的請求権
- 結論の妥当性
「請求が認められる」の意味とは
ある問いかけについて、「請求が認められる」と答えるとき、それは具体的にどういう意味か。
結論として、「請求が認められる」というのは、請求権の行使が認められることを意味する。
請求権とは、他人に対して作為または不作為を要求する権利のことをいう。5
つまり、だれかに対して、なにかを「させる」または「させない」ことを要求する権利である。
そして、以上の記載にも表れているように、「請求が認められる」かを検討する際には、「請求権が存在するか」と請求権が存在するとして「その行使が認められるか」という二段階の検討をする必要がある。
請求権が存在しなければ、その行使という概念は観念できないし、その行使が認められなければ、請求権が存在したところで目的を達成できないからである。
したがって、請求権が存在すること、その行使が認められることが論証できてはじめて、「請求権の行使が認められる」といえ、「請求が認められる」ことになる。
民法における法的権利の基本的な種類
民法問題では、その中身として基本的に法的権利の存否や法的権利同士の衝突が問題となる。
法的権利とは、法的に認められた権利のことであり、請求権と抗弁権がある。
抗弁権は、他者からの請求に対して、それを拒めることが法律上認められている権利である。
請求権の意義は前述のとおりである。
請求権には、物権的請求権や債権的請求権、その他の実体法上の権利がある。その他には親族法上の扶養請求権等が含まれるものの、主要なものは前の二つであるため、ここでは物権的請求権と債権的請求権についてのみ述べる。
物権的請求権とは、物権への侵害状態を解消することを要求する権利のことであり、物権の帰属主体が侵害主体に対して行使するものである。勝手に他人の物を使用する者に対して、所有権者が行使する、その物を所有権者に返還して所有権者が円満に物権を行使できる状態に回復することを要求する権利などがこれにあたる。
債権的請求権とは、債権関係に基づいて一方にその履行を要求する権利のことであり、債権者が債務者に対して行使するものである。合意に基づいて、一方当事者が他方の当事者に金銭を要求する権利がこれにあたる。
場合によっては、請求の主体が物権的請求権と債権的請求権の双方の請求権を有していることがある。この場合は、基本的に両方の請求権について検討するのが丁寧であるけれども、問題文中の比重によって分量に差を設けるべきであろう。
物権的請求権
物権的請求権は、民法上の明文を欠く権利である。
物権的請求権を導く民法上の規定は、占有の訴え(民法197条以下)である。
すなわち、民法は、占有が妨害されたとき(同198条)、占有が妨害されるおそれがあるとき(同199条)、占有が奪われたとき(同200条1項)に、それぞれ占有保持、占有保全、占有回収の訴えを提起できると定めている。
このとき、占有権より強力な所有権といった他の物権について、占有権と同様の訴えは提起できないと解釈することは、合理的な理由がない。
そのため、占有の訴えに対応する物権的請求権は、民法がそれぞれの物権を定めた条文に当然に内包された書かれざる効力であると理解すべきこととなる。いわば、当然の前提なのである。
占有の訴えに対応して、物権的請求権もその内容として以下の3つを有する。
- 返還請求権 : 占有(事実的に支配していること。)によって、物権の円満な行使が妨げられているときに、その占有を解き、権利者の占有下に物を返還させる請求権のこと。
- 妨害排除請求権 : 占有以外の方法によって、物権の円満な行使が妨げられているときに、その方法をやめさせることで、妨害状態を排除させる請求権のこと。
- 妨害予防請求権 : なんらかの方法によって、物権の円満な行使が妨げられるおそれがあるときに、そのおそれが生じている原因を取り除かせることによって、妨害状態の予防させる請求権のこと。
返還請求権と妨害排除請求権の区別は、「返還」まで必要かどうかを意識すればわかりやすい。
たとえば、自分の土地に無断で車が駐車されている場合、その駐車部分に対する物権の円満な行使は妨げられているけれども、その他の部分への物権の円満な行使は妨げられていない。このような状態で、「土地を返還せよ。」というのは、違和感がある。
物権の目的物を指して「返還せよ。」としているのであるから、それは物権の目的がほとんど達成できないほどにまで奪われているという場合に限られるはずである。
そのため、一部への物権の円満な行使が妨げられているに過ぎない場合には、占有されたとまではいえず、占有以外の方法による妨害であるとして妨害排除請求権を選択すべきと解される。
答案上で記述する際には、返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権のいずれかを書けば物権的請求権であることを述べていることが明白であるから、わざわざ物権的請求権という単語を登場させる必要はない。
もっとも、これら3つのうち一つを書いたとしても、いまだに請求の内容としては漠然不明確である。そのため、答案においては、さらに進んで具体的な請求権まで記述する必要がある。
Xの土地にYが無断で甲車を駐車している場合を例として記述すると、次のようになる。
Xは、Yに対して、所有権に基づく妨害排除請求権としての甲車撤去請求権を行使する。
結論の妥当性とは
民法問題のなかには、結論の妥当性にも言及しなければ適切な解答ができないものがある。
このような問題では、いったんはある結論が導き出されることを摘示(てきし)したのちに、その結論は本当に妥当なのだろうかと問題提起をして最終結論を導いていく必要がある。
結論の妥当性を意識した法的分析は、司法試験委員会より直接明示的に「必要」と指摘されてもいる。7
では、そもそも結論の妥当性とは、なにを指しているのであろうか。
これを詳しく語ろうとするならば、一稿分まるまる用いなければならないため、ここでは簡潔に私の認識を述べよう。
結論が正義にかなっていることを指しているのである。
厳密にいうと、結論がその法が意図した正義にかなう目的に適合することを指している。
そもそも、一般に「妥当性」とは、妥当な性質を有していることを指す。「妥当」の指す意味としては「適切であること」8などと説明されたりする。
もっとも、単に「適切」とだけ述べたところで、いったい何をもって適切かはまだ定かでない。与えられた法律という規範にしたがって導かれた結論であれば適切であるとも言い張れよう。
そこで、ここでは「正義」という語を用いて、「正しさ」が重要であることを強調していきたいと思う。
この「正しさ」は、法から導かれるという意味での論理的な正しさはもちろん、その法が意図する道徳的な正しさをも有していなければならない。同じく「正しさ」という言葉で語ることができるからである(もっとも、法を離れることはできない。法を離れて「正しさ」を語ってとしても、それはもはや法学ではなく倫理学や宗教学だからである。)。
優れて民主主義的人権主義的な枠組みが整っている我が国においては、法の支配の名のもとに、すべての法がさまざまな正義を意図して定立されおり、かつそのように解釈できなければならない。もし、このような解釈ができないならば、それは何かしらで我が国の憲法規定に違反し無効である。
したがって、すべての法は正義を意図しているところ、ある法を形式的に適用してはその法が意図する正義が達成されない若しくはその正義と適用目的が乖離してしまうような場合には、その適用はその法が意図した正義にかなうものではなく、その適用は否定されなければならない。
その適用を許しては、(その適用に限って)正義に基づかない不当な法が存在すること(いわば矛盾)を認めなければならなくなるからである。
では、法の正義にかなわない適用がされようとするとき、いかにしてその適用を否定できるか。
先にも述べたように、原理的には法の支配にかなわないものとして何らかの条項にしたがって憲法違反とすべきであるけれども、憲法違反といった究極の手段を用いずとも、単に法の要件を満たしていないとしてその適用を否定すればよい。
もっとも、法の要件を満たしていないというときには、その要件を文言解釈あるいは趣旨解釈等を駆使して限定的に解釈する必要があるけれども、それをするのは苦労が多く、また社会規範としてのわかりやすさが低下しかねない。
そこで、民法は、一般条項とよばれる規定を定めている。
この一般条項は、すべての私法関係に影響力を行使する存在であり、すべての私法が有している共通の正義観念を抽象化して示しているものということができよう。
このような一般条項の存在意義は、書かれざる法の要件を補完し、正義にかなわない法の適用を排斥できる直接の根拠となるところにある。
そのため、個々別々の法の要件を限定解釈することが困難である場合には、むりやりその場で理論を組み立てるのではなく、一般条項を用いて正義を実現すればよい。
(そもそも、もはや規定追加ともいえるような解釈は、法解釈が司法府の専権だとしても、立法府に介入する性質を有しているから、三権分立の観点からして慎重にならなければならない。したがって、このような困難が伴う解釈になる際には、一般条項によって解決を図れないか検討すればよいのである。)
ここまで来れば、結論の妥当性の検討の仕方は次のように明白である。
- 法が意図している正義にかなう目的を探し出す。
- 法が定める形式にしたがって論述した結果が1.の目的に適合するかを検討する。
- 2.の検討の結果1.の目的に適合しないのならば、その結論が妥当でない旨指摘する。
- 要件解釈による解決が容易な場合にはこれにより、困難な場合には一般条項による解決を模索する。
- 一般条項による場合には、適切な一般条項を選び出し、その一般条項の要件に従って具体的な事案を検討して結論を導き出す。
この検討の結果、結論の妥当性を確保できればそれで論証を終わってよい。
もし、それでも結論の妥当性を確保できなければ、その正義に沿わない程度と法が適用されないことによる不利益(個人の不利益といった私益や法益安定性といった公益)とを比較検討し、その結論でも致し方ないとするか、法の要件の限定解釈に本格的に乗り出すことになろう(もっとも、後者のように本格的に限定解釈を行おうとするのは、文字数的にも極めて困難を伴うため、答案においては選ぶことができないことが実情であろう。)。
以上が基本的な内容である。これより詳しい内容は別稿で個別の問題を解きつつみていきたい。
おわりに
今回は、はじめに述べたように、文章自体の内容ではなくその大枠について述べた。
今後も、適宜修正しながら、自らの理解の整理と復習としながらも、よりよい伝え方を模索していきたい。
また、内容面についても、ぜひとも批判的な目線からの検討を忘れないようにしてほしい。
以上
【補足および参考・引用文献】
- 美濃部達吉『-美濃部達吉論文集第4巻-公法と私法[再版]』24-25頁(日本評論社、1937)参照
※ 公法と私法について、率直に説明している資料を著者が有していなかったため、これを参考として引用した。たいへん古い文献ではあるものの、ここで「最も普通の説」と紹介される「主体説」は、今日においても通用するものと考えられる(※旧字体は新字体に代えて記載している。)。 ↩︎ - 令和6年司法試験民事系第1問 ↩︎
- 令和3年度司法試験民事系第1問 ↩︎
- 平成18年度新司法試験民事系第1問 ↩︎
- 中田裕康『債権総論[第五版]』24頁(岩波書店、2025) ↩︎
- ここでの見解は、いわゆる要件事実における権利阻止事由にあたるものの解釈を広げるものではない。すなわち、「その行使が認められるか」については、信義則(民法1条2項)や権利濫用(同条3項)、一般に権利阻止事由とされている同時履行の抗弁権(同533条)や留置権(同295条)などにつき検討すればよい。本稿は、一般的に権利障害事由と解されているものについて、権利阻止事由と解すべきとの立場を採っているわけではない。一般的な理解と同様の立場に立つものと考えている。
詳細については別稿にて詳述するつもりであるところ、多少触れておきたい。例えばいわゆる占有権原の抗弁については、一般に権利障害事由と解されている(司法研修所『紛争類型別の要件事実-民事訴訟における攻撃防御の構造-[4訂]』55頁(2022))ところ、占有権原の抗弁について権利阻止事由であると解すべきとの見解も存在する(橋本昇二『要件事実原論ノート-第3章-』白山法学、49-56頁(東洋大学法科大学院、2012))。
後者の見解は、占有権原の抗弁について、権利障害事由と権利阻止事由の両方とも解釈としてあり得るとしたうえで、権利阻止事由と解する方が自然であるとする。その主張の中身は理解できるところがあり傾聴に値するものと考えられる。しかし、占有権原の抗弁を権利阻止事由と解釈することは、民法の規定ぶりを俯瞰してみたときに疑義が入りえないだろうか。すなわち、占有権原があるということは、当事者間で合意をしたか、もしくはその占有を許容する法文が存在することを意味するはずである。このとき、物権的請求権であるといっても、物権そのものとは異なるのであるから、常に存在していなければならないと解する理由はない。民法等において賃借権や地上権といった権利が堂々と認められているのに、それと同時にその権利の存在を脅かす物権的請求権も存在しているとの建前が採用されていると解釈するのは、違和感がある。このようなときには、もはや物権的請求権が存在しないとの合意があったとみる、または法的にみて存在しないものと扱うのが民法の趣旨であると解釈する方が、むしろ自然であるように思われる。したがって、本稿としても、後者の見解は採用せず、一般的な理解である権利障害事由と解する。この理解と本稿に記載の内容は矛盾がないはずである。 ↩︎ - 令和5年司法試験の採点実感-民事系科目-6頁 ↩︎
- 小学館『デジタル大辞泉』 ↩︎
- 損害賠償請求の除斥期間の主張と信義則または権利濫用に関するものとして最大判令和6年7月3日民集第78巻3号382頁 ↩︎
- 最判平成22年4月13日民集第234号31頁 ↩︎
- 刑事法である刑事訴訟法には、「上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」という規定がある(第411条柱書、令和7年7月22日施行刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号))。
この規定は、同405条各号の上告事由がなかったとしても、各号にあたる限り「正義に反する」という理由をもって同405条の規定を無視して上告できると定めるものである。つまり、「正義」の観念が登場していて、かつそれが究極の例外的存在、すなわち、もっとも根本的な観念ゆえに覆すことができず決して反することを許さない存在として「正義」が持ち出されているのである(同411条各号は、正義に反するすべての場合が類型的に分けられているだけで、(著しく)「正義」に反していながら上告できないという場合は存在しえないと考えらえる。)。
このように、刑事法の分野においては、具体的な法解釈から「正義」の根本性を導き出せるのだけれども、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)にはこのような規定はなく、「正義」という文言が登場しないのである。
にもかかわらず、最高裁判所は、法的安定性が極めて強く要請される民事訴訟法において、その中でもさらに厳格な法的安定性が求められる確定判決という存在についても、(著しく)「正義に反」する特段の事情があるときには、これを実質的に覆すことができるとしたのである。ここに、条文の存在に関係なく、「正義」こそが民事刑事問わず広く法に関して妥当する根本的な観念であると解釈できるという意義が、この判例にあるといえよう。 ↩︎